INFORMATION
-

【イベント情報】2025年度『認知症と共に歩む市民講座』を開催します
崇徳厚生事業団では、認知症の予防から診断後の本人と家族のサポート、医療と介護のサービス提供を幅広く行っています。 2023年秋に米百俵プレイス北館において、認知症の初期診断から診断後のフォローアップ、介護相談まで幅広く対応する認知症専門の『すとく・おれんじクリニック』、認知症のみならず医療・福祉のお悩みをなんでもワンストップに相談できる『医療・福祉よろず相談』を開設し、「認知症の人と家族への一体的支援事業」もスタートしています。 認知症支援の拠点となるこの場所から、認知症にまつわる学びを深める機会として、『認知症と共に歩む市民講座』を開催いたします。 今年度は全10回シリーズで開催いたしますので、是非ご参加ください。 <日程・プログラム> ① 2025/6/28(土)14:00~15:00@米百俵プレイス北館 崇徳厚生事業団インフォメーションセンター 『糖尿病と脳の健康を考える~糖尿病と脳のちょっと気になる関係~』( チラシPDF ) ② 2025/7/26(土)11:00~12:00@米百俵プレイス北館 崇徳厚生事業団インフォメーションセンター 『しっかり食べて認知症予防』( チラシPDF ) ③ 2025/8/23(土)11:00~12:00@米百俵プレイス北館 崇徳厚生事業団インフォメーションセンター 『認知症患者における訪問看護の役割と必要性~看護師が訪問するメリットとは~』 ④ 2025/9/27(土)14:00~15:00@米百俵プレイス北館 崇徳厚生事業団インフォメーションセンター 『レカネマブ治療における認知症の早期治療の意義』 ⑤ 2025/10/25(土)11:00~12:00@米百俵プレイス北館 崇徳厚生事業団インフォメーションセンター 『認知症の人と家族の双方を支える役割~認知症ケアマネジメントの現状と課題~』 ⑥ 2025/11/22(土)11:00~12:00@米百俵プレイス北館 崇徳厚生事業団インフォメーションセンター 『認知症の人と家族との歩む暮らし』 ⑦ 2025/12/27(土)11:00~12:00@米百俵プレイス北館 崇徳厚生事業団インフォメーションセンター 『小規模多機能型居宅介護の役割と有効性~自宅と施設の間の「ちょうどいい」の実践報告~』 ⑧ 2026/1/24(土)11:00~12:00@米百俵プレイス北館 崇徳厚生事業団インフォメーションセンター 『認知症の早期診断と診断後支援の効果~米百俵プレイス北館事業と認知症疾患医療センターの取り組み~』 ⑨ 2026/2/28(土)11:00~12:00@米百俵プレイス北館 崇徳厚生事業団インフォメーションセンター 『認知症対応型サービスの今~認知症の個別ケアの現場では何が行われているのか~』 ⑩ 2026/3/28(土)11:00~12:00@米百俵プレイス北館 崇徳厚生事業団インフォメーションセンター 『認知症の人と接するときの心構え』 <概 要> 参加対象者:認知症に興味がある方 講師:崇徳厚生事業団グループ職員及び外部講師 参加費:無料 ※交通費、駐車場料金はご負担願います。なお、米百俵プレイス北館の立体駐車場ご利用の場合は、入庫から55分間の無料処理を行いますので、駐車券を会場までお持ちください。 参加申込:当日までに下記連絡先へ電話またはメールにて参加意向をご連絡ください。 <お問い合わせ・お申込み> メール:orange[at]sutokukai.or.jp ※[at]に@マークを入力してください。 電話:0258-39-7374(医療・福祉よろず相談) 『認知症と共に歩む市民講座』チラシ(PDF) -

【お知らせ】「老年問題セミナー2025」を開催します
2025年に到達し、次の2040年に向け、「地域包括ケアシステム」の今後の展望についての学びの機会として、『老年問題セミナー2025~『地域包括ケアシステム』の今後について~」を開催します。(主催:(一社)崇徳厚生事業団、後援:新潟県・長岡市・新潟県医師会・長岡市医師会・新潟県社会福祉協議会・長岡市社会福祉協議会、ほか) ■日程 2025年2月15日(土) 10:00~17:00 ■会場 ホテルニューオータニ長岡 NCホール (〒940-0048 新潟県長岡市台町2丁目8ー35) ■内容 講演1「これからの社会保障のあり方」 (一般社団法人 未来研究所 臥龍 代表理事 香取照幸さん) 講演2「地域包括ケアシステムにおける医師会の役割」 (松戸市医師会 会長 川越正平さん) 講演3「2040年を見据えた医療・介護施策について」 (厚生労働省 厚生労働事務次官 伊原和人さん) トークセッション ■参加費 5,000円(学生1,000円) 懇親会費:5,500円 ※懇親会は参加希望者のみ ■参加申込方法 Googleフォームより必要事項を入力・送信し、お申込みください。 ※参加申込期限:令和6年1月31日(水) ※定員(200名)に達した場合は先着順 ■お問い合わせ先 老年問題セミナー2025事務局(高齢者総合ケアセンターこぶし園内) 担当者:舩越、髙橋、大矢 ☎0258-46-6610 ✉rounenmondai@kobushien.com -

【イベント情報】『認知症と共に歩む市民講座』を開催します
崇徳厚生事業団では、認知症の予防から診断後の本人と家族のサポート、医療と介護のサービス提供を幅広く行っています。 2023年秋に米百俵プレイス北館において、認知症の初期診断から診断後のフォローアップ、介護相談まで幅広く対応する認知症専門の『すとく・おれんじクリニック』、認知症のみならず医療・福祉のお悩みをなんでもワンストップに相談できる『医療・福祉よろず相談』を開設し、「認知症の人と家族への一体的支援事業」もスタートしています。 認知症支援の拠点となるこの場所から、認知症にまつわる学びを深める機会として、『認知症と共に歩む市民講座』を開催いたします。 今年度は全6回シリーズで開催いたしますので、是非ご参加ください。 <日程・プログラム> ① 2024/10/12(土)10:00~11:30@ミライエ長岡 ミライエステップ 『認知症の人の排泄の問題』 ② 2024/11/30(土)11:00~12:00@米百俵プレイス北館 崇徳厚生事業団インフォメーションセンター 『認知症の心理状態』 ③ 2024/12/28(土)11:00~12:00@米百俵プレイス北館 崇徳厚生事業団インフォメーションセンター 『役に立つ認知症症状の理解』 ④ 2025/1/25(土)11:00~12:00@米百俵プレイス北館 崇徳厚生事業団インフォメーションセンター 『在宅と介護施設の選択のヒント』 ⑤ 2025/2/22(土)11:00~12:00@米百俵プレイス北館 崇徳厚生事業団インフォメーションセンター 『対応が異なる認知症あれこれ』 ⑥ 2025/3/22(土)11:00~12:00@米百俵プレイス北館 崇徳厚生事業団インフォメーションセンター 『認知症の予防と治療』( チラシPDF ) <概 要> 参加対象者:認知症に興味がある方 講師:崇徳厚生事業団グループ職員及び外部講師 参加費:無料 ※交通費、駐車場料金はご負担願います。なお、米百俵プレイス北館の立体駐車場ご利用の場合は、入庫から55分間の無料処理を行いますので、駐車券を会場までお持ちください。 参加申込:当日までに下記連絡先へ電話またはメールにて参加意向をご連絡ください。 <お問い合わせ・お申込み> メール:orange sutokukai.or.jp ※空白に@マークを入力してください。 電話:0258-39-7374(医療・福祉よろず相談) 『認知症と共に歩む市民講座』チラシ(PDF) -

【イベント情報】『フェスティバル白岩2024』を開催します。
令和6年4月より社会福祉法人 長岡福祉協会が指定管理しているコロニーにいがた白岩の里にて、『フェスティバル白岩2024』を下記のとおり開催します。 各種ステージ発表や作品展示のほか、食品や衣類などの販売ブース、認知機能チェック、骨密度簡易測定などの体験ブースがあり、どなたもでも入場無料となっております。 是非お越しください。 ■会場 コロニーにいがた白岩の里 体育館(長岡市寺泊薮田6789番地4) ※駐車場有 ■日程 2024年10月4日(金)9:30~15:00 イベントチラシ(PDF) -

【イベント情報】『第41回 太陽の広場』を開催します。
このたび、第41回太陽の広場を下記のとおり開催いたします。 各種ステージイベントと、キッチンカーなどの飲食が楽しめるイベントとなっておりますので、どなたもぜひおいでください。 ■会場 長岡医療と福祉の里 太陽の広場特設会場(長岡市西津町字原4668番地) ※長岡駅前~田宮病院前の無料バス有り ■日程 2024年9月29日(日)10:00~14:00 <ステージイベントプログラム> 10:00~ オープニング 10:15~ ダンス(えくぼクラブ) 10:45~ 悠久太鼓(長岡技術科学大学/鶴亀会) 11:20~ 祭囃子(河内御子翁保存会) 11:40~ しゃぎり(羽黒人形保存会) 13:00~ 吹奏楽演奏(帝京長岡高校) 13:50~ エンディング ※雨天中止の場合があります。 イベントチラシ(PDF) -

ひまわりスマイルプロジェクト(崇徳厚生事業団Letter令和6年8月号)
崇徳厚生事業団グループが取り組んできた農福連携の一環として、今年度は田宮病院近隣の畑にてひまわりの栽培を行っております。 『畑にも患者さんにも、大輪の花と笑顔の花を咲かせよう!』のコンセプトのもと、4000㎡もの畑地に約7000本ものひまわりが咲き誇ることを目指して5月から準備を始め、8月の中旬頃からひまわりの花が咲き始めました。 今回の崇徳厚生事業団Letterでは、ひまわりスマイルプロジェクトへの想いと、ひまわり栽培の様子について、プロジェクトリーダーの新保さんに伺いました。 ―ひまわりスマイルプロジェクトの意義について教えてください。 農福連携は農林水産省や厚生労働省など国も推進している取り組みで、農業労働力確保や農地の荒廃防止など農業側のメリット、雇用の場の確保や多様な生きがいなどの福祉側のメリットが上手く合わさることが理想です。 野菜の栽培から販売などがイメージしやすい農福連携ですが、これまで崇徳厚生事業団グループで取り組んできた農福連携には課題もあり、今年度は農福連携への足掛かりとして田宮病院を中心にひまわり栽培に取り組むことになりました。 ひまわりの栽培は収穫物の販売・活用や売上収入には繋がりにくいですが、初心者でも育てやすく、開花したときには大きな満足感と達成感が得られます。 「農福連携」とまではいかずとも、まずはその手前の「レク活動」として、患者さん・利用者さんには自然の中に身を置くことによる心身へのプラス効果や、自らの手で種をまき育てることによる達成感と社会コミュニティの参加機会の獲得に繋がればと考えました。 また、プロジェクトチームは田宮病院の様々な部署の職員を中心に農作業に興味があるスタッフで構成し、職員にとってもやりがいや隠れた力の発掘、専門外活動を通じた患者さんやスタッフとの交流や充実感の獲得などに繋がることも考えました。 ―ひまわりスマイルプロジェクトのこれまでの過程について教えてください。 6月7日にプロジェクト活動をスタート。堆肥の分散作業をはじめとした土づくりから開始しました。 6月12日には化学肥料と有機石灰を散布し、その後の耕起作業と畝づくりは農家の方にお願いしました。 土づくりは地道な作業で日によっては気温が30℃近くまで高くなるなか、皆さん一生懸命作業してくださいました。 6月19日からいよいよ種まきをしましたが、プロジェクトメンバー一人ひとりに専用の畝を設けて、全6種類の品種から好きな種を選んで蒔いていただきました。 また、畝をつくらない放置栽培エリアには観賞される方が通路として歩けるようにと防草シートを張りました。 几帳面に真っ直ぐシートを貼ったグループと、勢いよく味のある通路を貼ったグループとでそれぞれ個性の違いが出た2本の通路が完成しました。 7月に入ると雨が続く時期もあり、畑全体に海のような草が生い茂りましたが、汗を流しながらの毎週の除草作業に精を出しました。個体差はあるもののひまわりも比較的順調に育ち、メンバー専用畝では次第に品種の違いが見られるようになりました。 8月下旬が開花時期と予想していましたが思いのほか成育状況が良かったため、8/21~9/11を観賞期間とした「ひまわり鑑賞のご案内」を各事業所へ配布させて頂きました。8月21日には既に満開に近くなるかもしれません。 残念ながら8/25の雨風で一部倒れてしまったエリアもありますが、メンバー専用畝エリアではこれから見頃を迎える品種もありますので、この機会に7,000本のひまわりが咲くひまわり畑にぜひお越しください! 後列中央で弾ける笑顔を見せる新保プロジェクトリーダーとプロジェクトメンバーの皆さん -
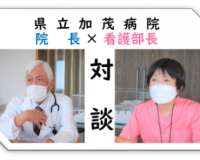
『県立加茂病院指定管理開始記念 院長×看護部長対談』(崇徳厚生事業団Letter令和6年5月号)
加茂病院の富所隆院長(左)と佐々木美奈子看護部長(右) 県央基幹病院の開設を目玉とした県央圏域医療再編の一環として、新潟県立加茂病院は指定管理者制度により令和6年4月より社会医療法人崇徳会が運営を担うこととなりました。 生まれ変わった加茂病院を引っ張っていくべく新たに就任した富所隆(とみどころ たかし)院長と佐々木美奈子(ささき みなこ)看護部長にお話を伺いました。 ―新しい加茂病院の役割をどのように考えていますか? 富所院長「いままでは、『加茂の医療は加茂病院で』と地域ごとに捉えていた部分もあると思います。しかし、医療再編により、地域住民の皆さまには、県央全体で一つの医療圏と捉えていただきたいと考えています。急性期や特別な医療行為が必要な患者は県央基幹病院で、回復期・慢性期の患者は県立吉田病院やこの加茂病院でと役割分担の明確化が図られています。加茂病院は、これまで以上に地域のかかりつけ医として関わる機能を大切にしていかなければならないと感じています。」 佐々木看護部長「富所院長と同じく、地域住民の皆さまに私たちの役割を理解していただきながら進んでいくことがカギです。新たな加茂病院の職員一同は明るく進んでいきますので、どうぞよろしくお願いします。」 ―院長・看護部長に就任されるにあたって、大切にしたいことを教えてください。 富所院長「一番は病院で働く職員のやりがい・生きがい、そして、楽しく働ける職場づくりです。様々な経歴や価値観・人生観を持つ職員が集まってくれましたが、『全ては患者のために』というベクトルを共有したうえで、多様性を活かして新しい加茂病院をより良いものに創り上げてほしいです。そのために職員の皆さんには『コミュニケーション』『挨拶』『笑顔』を大切にして、働きがいを感じて前向きに楽しんでいただきたいです。」 佐々木看護部長「『地域貢献』を大切にしたいです。一人ひとりの職員のやりがいの積み重ねによってサービスが深まっていく良い連鎖を作っていきたい。でも、最初からそれだけを求めては職員が緊張しすぎるので、まずは職員同士がお互いをおもんぱかる『協働の精神』を大切にして、患者さんを大切にしていくことで地域貢献に繋がっていくと思います。看護部全体を見回して、『この子は今日は笑顔で帰ったな』とか、『一昨日やれなかったことが今日やれてる』とか、人間の成長や明るさ・喜びの姿を見るのが管理者としては喜びです。『みんな絶対成長させてみせる』といつもそればかり考えています。」 富所院長「患者の一番近くにいる看護師が喜んでいると患者は喜びます。看護師が生き生きと働いている病院は絶対に良い病院なので、看護部長の責任は重いです(笑)」 佐々木看護部長「それぞれの部署に素晴らしい師長が着任してくれているので大丈夫です!自信を持っております!」 ―挑戦したいことを教えてください。 富所院長「県内一の慢性期病院・回復期病院にしたいというのが夢です。10年はかかりそうだし、それまで私が生きているかわかりませんけど。(笑)慢性期医療は、一人の患者へ時間をより長くより有効に使うことが出来ます。検査数値を改善したり痛みを取るだけでなく、人間を全部まるごと看ることで、その人の健康をより支えられることが喜びです。その患者が残りの人生で何を一番大事にしていきたいのかも含めて理解することで提供できる医療を目指したいと思っています。」 佐々木看護部長「私自身の経験を活かして職員満足を高めていきたいです。きちんと自分の強みや弱みを把握しつつ、反省と成長を繰り返していって、少しずつ職員満足を高めていきたい。加茂病院は比較的職員数も少ないので、職員満足度調査は手間を少しかけてでも丁寧に実施して、職員が抱える不安や不満を拾い上げていきたいですね。」 ―崇徳会の仲間に加わるまでは別の環境で経験と実績を積んでこられたと思いますが、崇徳厚生事業団や崇徳会の印象を教えてください。 富所院長「皆さん挨拶もしっかりとしてくれますし、皆さん笑顔で迎えてくださって、すごくアットホームで温かい医療法人だと感じました。また、慢性期医療、高齢者のための医療を大切に提供し続けてきた実績を感じ取ることが出来ました。私が最初に崇徳会や長岡西病院に抱いた温かさやほっとできるような感覚を、加茂病院にこれから訪れる人々も感じられるような職場になりたいと思います。」 佐々木看護部長「健全経営です。崇徳会は一時的に収益が落ち込む時期や事業所・部門があっても、全体バランスはしっかりと保って職員にきちんとお給料を払えているのはすごい。今年度は年2回の賞与においてもプラスがありましたね。みんなで頑張った分を職員に返すことができるのはとてもいいです。」 ―最後に、好きなことや趣味、休日の過ごし方について教えてください。 富所院長「最近は庭仕事と読書です。我が家はバラ園のようにバラがたくさんあって、一番多かったころは百種類くらいありました。昔は釣りやゴルフなどいろんなことに凝りましたね。動物もいろいろ飼いましたが、いまいるのは熱帯魚の水槽一つとケヅメリクガメの『カメ子』が一匹です。」 佐々木看護部長「休日は温泉巡りをしています。一番良かったお湯は秋田の玉川温泉ですね。かなり刺激が強くてびりびりするお湯で、湯治を目的に行く人も多い温泉です。普段はNetflixが楽しみですね。よく韓国ドラマを見ていて、全く別世界なので切り替えができます。韓国の俳優さんたちのプロ意識はすごくて、私たちを楽しませようと感動させようと演技をしてくれているのが伝わってくるし、やっぱり上手いですね!私たちも見習いたいなと思って観ています。」 加茂病院PRアニメーションを制作し、TVCM放映中です!コチラよりぜひご覧ください! -

【お知らせ】「老年問題セミナー2024」を開催します
2025年が目前に迫るいま、ポスト2025年を見据え、次の2040年に向かっていくために、地域共生社会の基盤となる「地域包括ケアシステム」を持続可能な仕組みとして深化・進化させていくための学びの機会として、『老年問題セミナー2024~とうとう2025年そして2040年に向けて~」を開催します。(主催:(一社)崇徳厚生事業団、後援:新潟県・長岡市・新潟県医師会・長岡市医師会・新潟県社会福祉協議会・長岡市社会福祉協議会、ほか) ■日程 2024年2月17日(土) 10:00~17:15 ■会場 ホテルニューオータニ長岡 NCホール (〒940-0048 新潟県長岡市台町2丁目8ー35) ■内容 講演1「地域医療編成について」 (厚生労働省 医政局 地域医療計画課 医療安全推進・医務指導室 室長 松本晴樹さん ほか) 講演2「地域包括ケアを担う人材の確保と育成」 (地域密着型総合ケアセンターきたおおじ 代表 山田 尋志さん) 講演3「尊厳のある看取りに向けて」 (株式会社ケアーズ 代表取締役 秋山 正子さん) 講演4「住まいとまちづくり」 (高齢者住宅財団 顧問 髙橋 紘士さん) ■参加費 5,000円(学生1,000円) 懇親会費:5,500円 ※懇親会は参加希望者のみ ■参加申込方法 Googleフォームより必要事項を入力・送信し、お申込みください。 ※参加申込期限:令和6年1月31日(水) ※定員(200名)に達した場合は先着順 ■お問い合わせ先 老年問題セミナー2024事務局(高齢者総合ケアセンターこぶし園内) 担当者:髙橋、大矢、吉井 ☎0258-46-6610 ✉rounenmondai@kobushien.com -

【イベント案内】中学生・高校生向け『医療・福祉のプロに会いに行こう2023』を開催します
中学生・高校生が若手の医療・福祉専門職との交流を通じ、仕事について知り、考える機会となるよう、『医療・福祉のプロに会いに行こう2023』を開催します。 ■日程 2023年7月27日(金)10:30~12:15 ■会場 長岡崇徳大学(長岡市深沢町2279-8) ※長岡駅前発着の無料送迎バス有り ■内容 ①若手専門職パネルディスカッション ②若手専門職とのフリー交流タイム ※終了後、希望する高校生を対象に「無料ランチ付きキャンパスツアー」を同日開催します。(長岡崇徳大学看護学科コース/長岡崇徳福祉専門学校介護福祉学科コースのいずれかを選択) ■参加申込方法 申込フォーム(Googleフォーム)より(申込期限7月21日(金)) ■お問い合わせ先 一般社団法人 崇徳厚生事業団事務局 担当:石坂 ☎ 070-8468-0558 ✉ jimukyoku@sutokukosei.com -

『私の自利利他』vol.10 訪問看護ステーションみつごうや(在宅リハ)(崇徳厚生事業団Letter令和4年12月号)
訪問看護ステーションみつごうやの訪問車に乗る大平さん 訪問看護ステーションとして新潟県内最大規模の職員数・訪問件数を誇る「訪問看護ステーションみつごうや」。 ここには看護師だけではなく、理学療法士などリハビリテーションの専門職も在籍していることをご存知だろうか。 大平茜(おおだいら あかね)さんは、医療法人崇徳会の3つのステーションを統合して、現在の訪問看護ステーションみつごうやとなった平成19年より前から、在宅リハビリテーション(在宅リハビリ)に従事してきた。 高校生のとき、病院見学でリハビリの現場をみて、「回復していく過程に一緒に関われるということが素敵に思えた」ことが理学療法士を志したきっかけ。身体を大きく一緒に動かしたいと思ったことも、理学療法士に絞った理由の一つだった。 長岡西病院に入職後、数年で在宅リハビリに従事するようになり、以後は訪問リハ一筋で経験を積んできた。 大学の卒業研究も在宅における維持期のリハビリを題材とするなど、もともと訪問リハビリに携わりたいと考えていたが、「ベテランになったら訪問に行けると思っていたので、こんなに早く訪問リハに行かせてもらえるとは思っていなかった。」とのこと。 退院後の生活を一緒に組み立てていく 訪問看護や訪問介護に比べると、在宅リハビリはまだなじみがない方も多いかもしれない。 しかし、地域包括ケアシステムのなかで在宅リハビリは、病院で入院中に行うリハビリとはまた異なる役割を持っている。 「例えば高齢の患者さんが骨折や脳梗塞で入院し退院されると、入院前後で生活がガラッと変わってしまうことがあります。入院中のリハビリで身体機能や能力を向上させて退院しますが、以前の状態までは戻れないことも多いからです。 住み慣れたご自宅ですが、入院前と退院後では身体機能が変わってしまうので、同じ環境だから同じことが出来る状態とは限りません。 病院でももちろん在宅復帰を想定し、退院前にご自宅に訪問して環境整備をしたり、ご自宅の環境を踏まえたリハビリを提供して生活能力を上げて退院出来るよう努力していると思います。 それでも、病院とご自宅とではやはり環境が違うので、身体機能的に病院で出来ていたことがご自宅で出来るとは限りません。整備した環境に適応出来ているか確認することも難しいです。 病院では退院後も続けてほしい訓練を患者さんに指導したり、家族に介護のやり方を指導したりしますが、患者さんが受けた指導のとおり訓練に取り組めるか、ご家族が指導のとおりに介護できるかはまた別です。 そういった観点からも、在宅でリハビリの目が入ることは必要です。それに、退院後の環境や生活状況を見させてもらうことで、もしかしたら患者さんやご家族により合ったご提案ができるかもしれません。 退院後はその方の生活がまた新たにはじまることになるので、一緒に生活を組み立てていく作業が必要だと考えています。」 退院後の生活を組み立てていく作業としては、リハビリや介護指導だけではなく、家具の配置や福祉用具の選択、時には住宅改修のために大工や工務店と一緒に仕事をすることもあるという。 退院後、リハビリを継続することで身体機能や能力がさらに向上したり、長い経過の中で加齢とともに低下する場合もある。そうした状態変化があれば、その都度目標設定や環境整備の再検討が必要になる。 かつては医療職でも訪問リハは何のために何をするのかよくわからないという方もいたが、徐々に医師やケアマネが理解されるようになったとのことだ。 提案するだけではなく、「一緒に考えていく」姿勢を持つ 在宅リハビリの仕事が病院のリハビリと違うのは当然ではあるが、大平さんが最も違いを感じるのは、リハビリを行う場所そのものよりも、利用者との関係性にあるという。 「在宅リハビリは利用者さんの生活の場、テリトリーに入らせていただいて、利用者さんは普段の生活の一部を使って私たちに向き合ってくださいます。 そういった意味で、病院で働いていたときとは心構えが違っています。入院中の患者さんと職員の関係性とはまた少し違った関わり方で、より利用者さんに近い立場になれると感じます。 利用者さんの生活の場でリハビリをさせてもらうことで、利用者さんの背景や人生をよく理解でき、その方に合ったご提案ができることはメリットです。 提案するときも、こちらから提案をするだけではなく、一緒に考えていくという姿勢を持つようにしています。 課題ひとつとっても、『いまここに困っているならここを考えましょう』とか、『私たちだけじゃ気づけないから、困っていることを教えてほしい』とか。 『相談相手にならせてほしい』という姿勢で関わることで、利用者さんから受け入れてもらえると感じます。 訪問だから必要な姿勢というわけではないと思うのですが、私は病院で勤務していたころは気づけていなくて、利用者さんの生活の場に入っていくことで感じ取れるようになりました。」 そんな大平さんでも、提案が受け入れてもらえないことも「いっぱいあります(笑)」とのこと。 「『上手くいかなかったな』で終わることもあります。そのほうが多いかもしれません。 ご家族など介護される方との関係性も見せていただいているので、『この方はどんな引き出しがいいのかな』と考えてあの手この手で関わっていったり……。 あるいは私たちがベストと思う時期と利用者さんが感じるベストの時期がズレていると思えば、時間を置いてみたり、他のアプローチを考えます。」 経験豊富な大平さんだが、現在、理学療法士による訪問は担当制であるため、「独りよがりになっていないか」という不安は常にあるという。 ステーションの統合前はリハ職が一人だけだったが、現在の「訪問看護ステーションみつごうや」はリハ職も複数人在籍していて、さらに、訪問看護師と利用者さんの情報共有もしやすい。 一人で抱え込まないようにと意識し、相談事は積極的に発信することで安心感に繋げているとのこと。 やりたかった在宅リハビリを続けてきて、変わらずにやりがいを感じて、今も楽しいと思えると語ってくれた大平さん。 最後に、未来の仲間に向けてメッセージをいただいた。 「理学療法士だけでなく、『訪問』の仕事はベテランにならないと出来ないというイメージがあって、やりたくても一歩踏み出せない人も多いと思います。 でも、助けてくれる仲間がたくさんいるので、お互いに支え合うことで『できます』。 訪問はすごく楽しいので、やりたいと思う人が増えてほしいです!」 <取材後記> お話を伺う中で、あらゆる場面で「あの手この手で・・・」「これなら受け入れてもらえるかな~と考えて・・・」等とお話しされており、経験で得た引き出しをたくさんお持ちで、常にご利用者様、ご家族様に寄り添った内容を提案・提供されているのが分かりました。 当初から希望されていた在宅リハビリを長年経験され、「いまでも楽しいと思える」とお話しされる姿はとても輝いていました。 (取材・編集:医療法人崇徳会 法人事務局 瀧澤 真紀子、崇徳厚生事業団事務局 石坂 陽之介) ʕ•ᴥ•ʔʕ•ᴥ•ʔʕ•ᴥ•ʔʕ•ᴥ•ʔʕ•ᴥ•ʔʕ•ᴥ•ʔʕ•ᴥ•ʔʕ•ᴥ•ʔʕ•ᴥ•ʔ Twitter、LINE公式アカウントで『崇徳厚生事業団Letter』更新情報を配信しています! フォロー&友達追加をお願いします! Follow @Letter_Sutoku ʕ•ᴥ•ʔʕ•ᴥ•ʔʕ•ᴥ•ʔʕ•ᴥ•ʔʕ•ᴥ•ʔʕ•ᴥ•ʔʕ•ᴥ•ʔʕ•ᴥ•ʔʕ•ᴥ•ʔ
